中小・ベンチャー企業がオープンイノベーションに取り組む際の考え方
中小・ベンチャー企業のオープンイノベーション実践に向けて、より具体的な成功・失敗の要因について解説~中小・ベンチャー企業が相互に連携を行う際の留意点について、筆者のこれまでの経験に基づき紹介する。大企業と比較して自社の経営資源が潤沢ではない中、いかにしてその不足を補い、むしろ逆手に取って技術の事業化を実現するか、という点がオープンイノベーションにおけるカギとなる。
さて、オープンイノベーションとは、社外のリソースを活用しながら、まだ世にない新しい製品・サービスを生み出そうという試みである。つまり、日常の業務の中で行われているような、部品の外注や委託加工のプロセスとは、そもそもの考え方が大きく異なる。
従って、外注における考え方をオープンイノベーションに持ち込んでしまうと、それは連携にブレーキをかける要因となりかねない(図1)。
ここでは、他社との連携の形態がこれまで外注のみだった企業を想定し、中小・ベンチャー企業同士のオープンイノベーションにおいて問題となりやすい項目について、基本的なポイントを解説する。既にオープンイノベーションへの取り組みを進めている企業においても、改めて取り組み方を振り返るための視点を提供したい。
☜ 左記の項目を参照。
[1]-1. 可能な限り外部資金を活用する
中小・ベンチャー企業同士の連携において、最初に問題になりがちなのは、他社と連携までして新しい技術や製品の開発を目指すだけのリソースの余裕がなく、話が立ち消えになってしまう、またはそもそも連携に取り組もうという意識すら持てないといった状況である。
お互いにリソースの少ない中で連携を図ろうというのだから、これは無理もないことともいえる。
幸いなことに昨今は中小・ベンチャー企業であっても、国レベルから地方行政レベルまで多様な公的機関から資金援助を受けられる。その内容も研究開発色の強いものから、全く研究開発を必要としない単なる市場調査まで、様々である。
まずは外部資金の獲得を目標に、目標や体制を定めていくのが、中小・ベンチャー企業同士の連携のスタート時点においては有効だろう。 そのような公的支援について、ほんの一部だが、表1に中小・ベンチャー企業が活用可能なものの例を掲載した。
地方行政は東京都を例として掲載しているが、もちろん他の道府県でも同様の支援は行われているので、自社の状況に合った公的支援を見つけて活用していくことが、オープンイノベーションの実施の際には有効である。
多くの場合、これらの外部資金を獲得するためには何らかのチェックを受けることになるのだが、チェックを乗り越えるだけの質の高い目標・計画を策定できれば、結果として連携の初期段階において重要な、事業構想の質の高さを担保しやすくなる。
ただし、この時点で立てた計画を絶対視し、方向転換の柔軟性を失うような事態は避けなければならない。この点について、詳しくは後述する。
[1]-2. 相手企業とは技術よりもビジョンを共有
中小・ベンチャー企業同士の連携において、特定の技術に関するピンポイントな支援を求める、といった連携のやり方はうまくいかない可能性が高い。
相手企業が自社の求める技術そのものを持っているように見えたとしても、その技術を自社の技術と組み合わせて事業化にまでたどり着くには、追加の研究開発が必要となる場合がほとんどである。
この点は、技術の外注とは全く発想を変える必要がある。
オープンイノベーションの成否を左右するのは技術そのものよりもむしろ、相手企業とビジョンを共有でき、先の見えない研究開発に付き合ってくれるかどうか、という非技術的な要素である。
よくある失敗パターンの1つが、自社が欲しい技術を相手が持っていると思って手を組んだのにもかかわらず、その後の連携がうまくいかなくなり、プロジェクトが停止するというものだ。プロジェクトが「うまくいった」と耳にするのは、事前に明確な目標を定めて始めた連携の場合よりも、逆に何をするか決まっていないまま始めて、お互いの方向性をすり合わせる中で研究テーマが決まったという連携の場合の方が、むしろ多い。
[2]-1. 計画が流動的であることを相手企業との共通理解としておく
これは中小・ベンチャー企業に限った話ではないのだが、オープンイノベーションに取り組む中で当初想定していた目標を変更する必要に迫られるというパターンは非常に多い。むしろ、最初から最後まで当初の目標通りに進んで事業が成功した、という話を聞くことはほぼないのではないだろうか。
大企業と比べて中小・ベンチャー企業はフットワークの軽さを強みとすべきであるのに、一度設定した目標にとらわれて、臨機応変な方向転換の動きが遅くなってしまっては本末転倒である。相手企業との連携体制の中で「双方の強みを持ち寄って実現できる最善のビジネス」を生み出す、という目標だけに意識を向けるべきである。そこで重要になるのは、計画の流動性についての相手企業との認識のすり合わせである。
自社が持ち込んだ話だからといっても、計画通りに進まない可能性を相手に伝えることをためらう必要はない。
認識を共有するのに加えて、可能であれば、相手企業においても社長や経営者の直轄プロジェクトとして位置付けてもらうことが望ましい。
少なくとも、現場で生じた問題が即座に意思決定者に共有され、方向転換が必要と思われる際にはスピーディーな判断を下せるよう、相手企業における意思決定のラインを自社が把握しておくことは必須である。
[2]-2. 相手企業を育成する覚悟を持つ
どんなに連携相手の経営者のビジョンが優れていたとしても、相手企業の現場レベルの研究開発能力や想定市場における知見が期待したほどでないと後から分かる、という事態は十分に起こり得る。
もし、相手企業の不足を補える能力が自社にあるのなら、自社の社員を育成するのと同様の活動を相手企業の社員に提供する選択肢も用意しておく必要がある。
とある中小企業A社が別の中小企業B社との連携を手掛けた際、B社の研究開発の進捗が悪く、B社の社長と話しても一向に改善の傾向が見られなかったという。
業を煮やしたA社社長は自らB社の工場に出向き、手取り足取り研究プロセスを教えることで、結果として期待した成果を無事得ることができた、といったケースがある。 こういった考え方は相手企業を長期的なパートナーと認識しているからこそ成り立つものであり、事前の信頼関係の構築が重要な前提となる。
[2]-3. 実用化のハードルを上げすぎない
中小・ベンチャー企業同士の連携においては、お互いにリソースの少ない中で新しいビジネスを生み出そうとしているのだから、これまで存在しなかったコンセプトを世に問う活動にリソースを振り向けるべきである。その実用化のハードルは可能な限り下げておく必要がある。
特に、大企業の下請けとして既存事業を持つ中小企業に多いのだが、高度な品質基準を満たした製品を取引先に納入する事業に慣れている企業は、オープンイノベーションによって生み出そうとする新たな製品・サービスにも同等の品質レベルを求めがちである。
しかしながら、高い品質基準を満たそうとすると、追加のリソースばかりが膨らんでしまう。
結局何の売り上げも生み出さない事業と見なされてしまうと、プロジェクトの立ち消えリスクが高まるものである。
このようなリスクを回避するためには、オープンイノベーションにより開発する製品・サービスの質を高めるのと並行して、最低限の完成度で販売できる市場を見つけておくのが望ましい。
その上で、現業を有する中小企業であれば、従来の品質基準と新事業の品質基準は「別に考える」こととして、顧客や社内の品質管理部門などを納得させる必要がある。
既存製品を持たないベンチャー企業であっても、実用化のハードルを下げておくように意識しておくべきであろう。
例えば、すぐには製品化しにくい技術について、テスト用サンプルとしての販売や技術のライセンシング、研究開発サービスとしての売り方など、高いハードルを越えなくても売り上げを生み出せる方法を考えておくのが重要である。
今回は、中小・ベンチャー企業同士でオープンイノベーションの実現に向けた取り組みを進める上でのポイントを、主に外注とオープンイノベーションの違いという切り口から紹介した。
規模の小さい中小・ベンチャー企業であるからこそ、業務の中で技術的な外注を活用する機会は意外にも多いものである。
オープンイノベーションの実施に当たっては上記のポイントを踏まえて、外注の考え方に引きずられることなく、頭を切り替えて取り組んでいただきたい。

著作権は日経BP、またはその情報提供者に帰属します。
※ メール・BLOG の転送厳禁です!! よろしくお願いします。


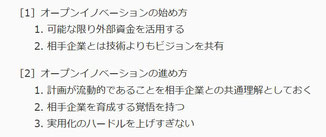

コメントをお書きください