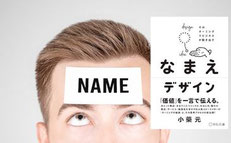
2023.06.12
by 毎日3分読書革命!土井英司のビジネスブックマラソン
思わず手にとってしまう、欲しいと思わせる、共感されるようなネーミングの商品ってありますよね。土井英司さんが紹介するのは、大ヒット商品のネーミングを手掛ける著者の一冊。「なまえは育てるもの」という考えを持った著者の仕事術は必読です。
プロが教えるネーミングの秘密⇒『なまえデザイン』
マーケティングの最小単位は「名前」だと考えています。
われわれ人間は、「名前」が付くことで、「それ以外とは違う価値を持つ」という認識を持つからです。
ビジネスブックマラソンでもこれまで、数多くのネーミング本を紹介してきましたが、本日ご紹介する一冊は、その中でもベスト5に入る一冊です。
著者は、元博報堂のクリエイティブディレクター/コピーライターで、これまでにネーミングやブランディングで数多くの実績をお持ちの小薬元(こぐすり・げん)さんです(「薬」は本来難しい方の字ですが、文字化けを避けるため、こちらで統一します)。
「まるでこたつソックス」
「パルコヤ」
「ジェリコ」
「小豆小町」
「からだにユーグレナ」
「SAKE HUNDRED」
などは、おそらく多くの読者が聞いたことがある名前ではないでしょうか。
著者は、「はじめに」で本書のことをこう語っています。
この本は、本屋の同じ棚に並んでいるかもしれない「ネーミングスキルを伝える趣旨の本」ではありません
理由は、2つあって、1つは「なまえは育てるもの」という考えを著者が持っていること。もう1つは、右脳と左脳をいったりきたり、くっつけたりして「なまえ」を生んでいるため、「売れるネーミングの作り方は3つ」みたいなビジネス書風の表現が軽薄に感じられるからなんだそうです。
この「はじめに」を読んだだけで、期待値が大きく跳ね上がったわけですが、読んでみて、それが確信に変わりました。
真にブランドとして「育つ」ネーミングを知りたい方、受け手に共感される言葉の法則を知りたい方は、ぜひ読むことをおすすめします。
さっそく本文のなかから、気になった部分を赤ペンチェックしてみましょう。
名前は「書くもの」というより「生きもの」。「名づける」というか「はじまる」もの
実はネーミングが、「もっと伝えたい」「もっと売りたい」「もっと目立ちたい」を解決する
縁起は担ぐ。神様は仰ぐ。時もある。
地域に名前をつけるだけで、特別になる不思議。ブランドになる。
さば→関サバ
明太子→博多明太子
牛乳→八ヶ岳牛乳
「はじまりになれる名前かどうか」「巻き込める名前かどうか」
保育FUTUREカンファレンス
(私は関係ないかも)
↓
保育をどうしよう未来会議
(私も関係したいかも)
料理家の平野レミさんは「アク」のことを「悪魔」と呼んでいます。それを聞くと、そのままにすることなく、もう絶対に取りたくなる
どう略されるかを先回りしよう
ウッドボックスではなく「ウーボ」なのは、生きもののような、飛行船のような語感を持たせたかったから
難しい音は、口の端に乗らない
肩が強い甲斐捕手→甲斐キャノン
「なまえ」がつくからメディアが紹介できる
名前=意味+気分
あたたまる
↓
まるでこたつぐらいあたたまる=差別化
ヒットネーミングは、仲間をたくさん増やせたから
「飲むユーグレナ」では何が少し問題か。
ユーグレナが何者かまだそこまで知られていない状況だとすると、「なぜ飲まないといけないの?」「ユーグレナってそもそも何?」と唐突に感じてしますのです。(中略)比べて「からだにユーグレナ」は、たとえ詳しく知らなかったとしても「ん?からだにいいのかな?」「良さそうなのかも」という初速スタートになるのではないでしょうか
土井もそれなりにネーミングには自信を持っているのですが、著者のように「やさしい」「共感される」ネーミングをどうしたら作れるのか、ずっと悩んできました。
本書を読んで、その秘密が少しわかった気がします。
SNS時代に共感・共有されるネーミング、ブランディングの秘密を知りたい方は、ぜひ、読んでみてください。
※ メール・BLOG の転送厳禁です!! よろしくお願いします。

コメントをお書きください